|
|
(0) 「集合 X からそのベキ集合 P(X) への全単射は存在しない。」
(通常はカントールの対角線論法とよばれる背理法で証明します。)
の直接証明は、より一般な次の定理から明らか:
(1) 「 f : X→P(X) は全射ではない ( Im(f)≠P(X) )。」
(数学科一年生の講義で使っている証明:板書では5行)
∵ B := { x∈X | ¬( x∈f(x) ) } ( ∈P(X) ) とおく。
x∈B ⇔ ¬( x∈f(x) )
( x は B か f(x) の一方のみの元であるから、B と f(x) とはその元が一致せず)
B ≠ f(x)∈Im(f)
(つまり、B は像 Im(f) のどの元 f(x) とも等しくないので、)
¬( B∈Im(f) )
(であるが、B∈P(X) であったから、)
Im(f)≠P(X) □
一行一行が正しく理解可能です。更にこの証明は、
「任意の写像 f にたいして、その像 Im(f) に属さない元 B を構成」
しているので構成的な証明です。
(%) ラッセルのパラドックス:
R:= { x | ¬( x∈x )} ( x は集合 )
を集合とすると・・・途中省略・・・矛盾が導かれる。
「集まり(クラス)=集合」と思っていた当時には、集合論が矛盾を含んでいるのではないかと不可解な思いをしたと聞きます。現代では、ラッセルのパラドックスは
(#) 「R は集合ではない」
ことの背理法を用いた証明と捕らえられます。但し、背理法を使っているので、当時は不可解であったのではないか思われます。これを、(1) の直接証明で、f=恒等写像とおけば次のように直接証明できます。
(#)の直接証明:
∵ R= { x | ¬( x∈x ) } より
x∈R ⇔ ¬( x∈x ) ( x は集合 )
クラスに関する外延性公理により、
R ≠ x ( x は集合 )
よって、R は集合ではない。□
つまり、R は定義から「任意の集合と等しくない」ので集合ではないのは当たり前のことと納得できます。つまり、「集合はクラスである」が、「R は集合ではない(真クラスである)」ので逆は成立しない。
なお、クラス概念まで考えないと理解は中途半端になり、「大きい集まり(真クラス)はコワい」という思考の妨げとなる。こういう人は、不必要なところにも常に「全体集合」を仮定しています。特に、背理法のままだと、あたりまえと思えず自信が無いことも影響していると思います。
[なお、「全体集合」を「普遍集合」という人がいますが、クラスを知る者には「普遍クラス」(これも真クラス)を想起させるので紛らわしい。「全体集合」は「(そこで考える)全体を限定する集合」ですから、「偏在」であり「普遍」とは逆の意味であるようにも思えます。]
上記の(%)「ラッセルのパラドックス」の箇所から、
ラッセル → ピュタゴラス
R → √2
集合 → 有理数
クラス → 数(実数)
と置き換えを行えば、ピュタゴラスが「数といえば有理数」と思っていれば、
「数論は矛盾を含んでいるのではないか」
と不可解に思うのも納得できます。背理法で証明しても、当たり前とは思えず、
不可解性(神秘性)は残ることとなります。
逆に、直接証明は当たり前の連続で、意外性神秘性は殆どありません。かといって、学生・生徒に印象に残るようにという配慮で「背理法」を使うとすれば、煙に巻くことと同じで教育的とは思えません。特に、中学生が3行で直接証明できる「√2 は無理数」を高校教科書で教えるのは不適切でしょう、(優秀な)生徒にバカにされるだけです。これは、大学でも同じです。
数学科の学生には、数学の専門書の「ある定理の背理法証明」をみつけたら、
「背理法を使うのは、著者がその定理が当たり前と理解できず説破詰っている」
という証拠だから、もし
「非背理法証明(どんなに長くても)ができたなら、
君が一行一行当たり前の連続として理解できている」
という証拠で、
「その定理に関しては、著者より自分の方が理解できている」
と自信を持っていいと指導しています。但し、
「その分野で使える定理を(理解度は低くても)知っているだけでも数学はできる」
という証拠にもなっていると,、理解偏重にならないよう注意を促しています。
誰でも思いつきそうな簡単な証明(教育的でもある?)を、大多数の集合論関係の本では、上記の(0)をカントールの猿真似の背理法で証明している。(0)
には背理法が必須であると、本に書いている大学教授もいる。この状況は、√2が無理数であることの背理法の証明に酷似しています。
背理法に慣れると、意味論的思考を停止せざるを得ないため、既存の背理法のパターンに束縛されてしまうのかもしれません。
なお、上記の定理(0)の証明で、部分集合の特性関数を使った非背理法による証明が、
上江州忠弘著、集合論・入門、遊星社
の p.120 定理 1.1 と p.121 定理 1.3 で述べられています。
この「集合論・入門」について特記すべきは、
最終的に
(a) 「選択公理」「整列可能」「ツォルンの補題」「濃度の比較可能性」
「無限基数 m について m=m^2 なること」の同値性や
(ここで、背理法を多用している本が大変多い。)
(b) 「一般連続体仮説が選択公理を含意していること」
まで示しているのに、
(c) 本文の[証明]には一切背理法が使われていない
ことです(私の見逃しがない限り)。
背理法がないので、すべての証明が一行一行理解できるし、
通常背理法を用いた証明部分も背理法より簡潔になっています。
(但し、(a)では若干の省略はありますが、
ここまで読んだ読者には補間(勿論、背理法を用いず)は可能です。)
また、この本では
(d) 論理記号が殆ど使われておらず、
平明な文章で厳密な考察(ほぼ公理的集合論レベルの)までしている。
私は論理記号依存症で、何でも論理記号に直さなくては解った気がしません。
論理記号により形式化された体系と異なり、
通常の数学専門書は頭の中で翻訳しながら読んでいくようで
内容を素手で掴んだ気がしません。
また、数学的意味内容を理解しないと翻訳は困難ですから、
背理法証明中の主張は大きな障害となります。
この「集合論・入門」は論理記号を殆ど使っていないのに、
同時通訳を聞いているように大変解りやすい。今まで読んだ本では、
ブルバキ数学原論(の背理法以外の部分)
が明快さが最高と思っていましたが、私的にはそれを超えている
と感じています(特に、背理法を使っていませんし)。
なお、ブルバキ数学原論は論理体系の段階で
「選択公理を含意する」もの(標準的古典論理体系より強い)
を採用しているので、これは私的には不満なところです。
学生が意識せずあたりまえのように「選択公理」を使うのを
助長してしまうと思うからです。
ブルバキ数学原論を読んでいないと思われる
数学者(標準的古典論理)が、
「選択公理が(論理的に)当たり前」(誤解)のように使ってしまうのを
不思議に思っていました。
この本(p.48-51)では
(e) 「存在命題を前提とする論証における論法」における「固有変数条件」の重要さと「選択公理」との関係に付いて詳述されていて、
上記の誤解の原因の一つが得心でき、論理教育に生かすことができました。
他にも、一般数学者によくある誤解(特に、公理的集合論を一般の数学に使う際にみられる)を示唆する教育的配慮が見られます。私が気付いたものでは、
(f) 等号、順序対、自然数、順序数、基数
の概念を早期に公理を用いて導入しています。この本のように、集合論で早期に公理を用いて導入しておけば(楽だし)、後に一般の数学に適用するときに安心です。
例えば、順序対や自然数は「公理的集合論」においては、
「順序対 <x,y>={{x], {x, y}} 」や「自然数 0=φ, 1={φ}, 2={φ, {φ}}, ・・・」
として「具体的に」定義(公理的には、一つのモデルに過ぎない)することもできますが、これだけが順序対や自然数の定義と思って一般の数学にも使えば矛盾が起こります。
本書のように、先に公理を述べその後にこれらの具体例が公理を満たすとすれば、誤解は生じにくいし教育的と思います。
特に、「2 集合の相等性」(p.12-15)の部分では、
「外延性公理」と「集合の相等性」に関してよくある誤解(混同?)の指摘をし(傾向)、
それに対して本書は「相等性の公理を初めから認める」(対策)が述べられている。
著者の指摘する誤解は、
初学者では問題点の存在さえ認識し難いと思うので、
半専門家に対する注意であろうかと思います。
実際、多くの著書に誤解をしているまたは読者(*)に誤解を与えると思える記述があります。
憂慮すべきことと思うのですが、逆に「集合の相等性」の部分をみれば、その本の著者のレベルの判定ができます。私が、数学科一年生の集合に関する参考書として唯一「集合論・入門」のみを紹介している理由の一つです。
[ (*)読者が「数学科学生」でなければ被害は少ないと思えます。
数学科学生は、「(公理的)集合論」と他の多くの公理系と整合性を持った教え方をしないといけないので、「集合論」を教えるのには非常に神経を使います。]
(g) 「集合論・入門」ではクラス(集合の一般化)の概念を使用している。クラス概念の効用は、(%) ラッセルのパラドックスの後に述べました。
上江州先生が東京理科大学理学部応用数学科(現数理情報科学科)
で教えていらしたとき、私も同理学部の数学科で論理と集合を教えていたり
数学基礎論を卒業研究で扱っていました関係上、
先生と数学基礎論に関するお話しする機会が度々ありました。
当時から私は背理法嫌いでしたから、
折に触れ背理法に関する話題も出して、
「背理法は意味論的にみて教育的でないこと」、
「多くの数学者が不必要な背理法を使っていて困る」
など申し上げていました。
私の主張には納得してくださったようなのですが、
大して問題にするようなことではないというような雰囲気でした。
「集合論・入門」をみて、このときの上江州先生の反応が納得できました。
上江州先生は、
「背理法は、やろうと思えばすぐに除去できる」ので
まさか私が
「背理法を除去することに苦労している」とは、
思いもよらなかったのではないかと想像します。
プロとアマの差以上に、未来人と原始人ぐらいの差を実感しています。
(これは、私にとっては大変励みになっています。)
なお、先生との会話の中で、
「選択公理仮定していないと、順序数の扱いが面倒です」
のようなことを申し上げたら、一言:
「公理を使ったらいいですよ」
とのご教示をいただき、それ以後講義等では大変楽をさせて
もらっています。
[以下では、自然数全体の集合を N と実数全体の集合を R で表します。]
(1)の系として、 P(N) から R への全単射は存在するので、
(2) 「 g : N→R は全射ではない。 」
更に、この系として、
(3) 「N から R への全単射は存在しない。」
が得られます。
(3) も、通常はカントールの対角線論法とよばれる背理法で証明しますが、
ベキ集合に関する上記の定理(1)を使わずに、
構成的な直接証明も可能で、(2)より一般な、例えば
(4) 「 g : N→R と閉区間 [a,b] (a<b) につき、[a,b] には像 Im(g) に属さない元が存在する。」
ことを証明できます。
なお、対角線論法はLawvereにより、
(不動点定理の形で)積閉圏へと一般化されています。
勿論、背理法は不要です。
F. W. Lawvere, Diagonal Arguments and Cartesian Closed Categories
(ネットで pdf 版入手可能。)
|
|
|
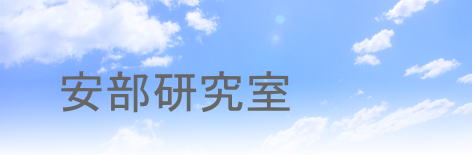 更新情報:HP
更新情報:HP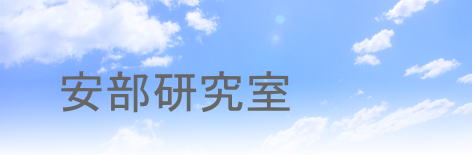 更新情報:HP
更新情報:HP